
東京都八王子市立第八小学校 特別支援教室主任教諭 川上 尚司
限局性学習障害にあたる児童、家庭が必要とする合理的配慮を得られる方法の研究
Specific Learning Disorder
第61回下中科学研究助成金取得者研究発表より
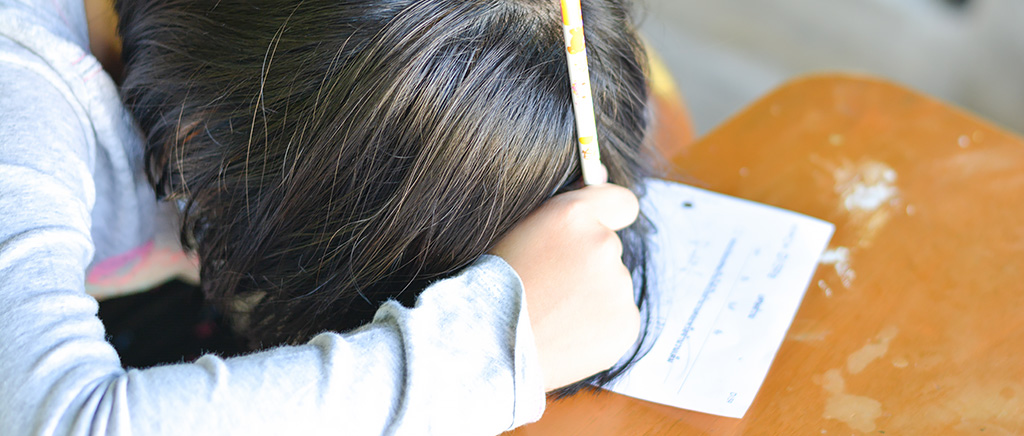
SLDの捉え方が医療分野と教育分野で異なるため、学校側がSLDを疑ったとしても、医療機関では異なる診断を示す場合がある。
1.はじめに 都合よく使われがちな”発達障害”
集中が続かない、立ち歩きが目立つ、喧嘩が絶えない児童や生徒を見ると注意欠陥多動性障害(ADHD)ではないか、こだわりが強く、他者の気持ちが想像しづらいと自閉症スペクトラム(ASD)ではないか、と決めつけてしまったり、学力が低いから知的障害と見なしたり、本人のやる気や努力が不足していると決めつけてはいないだろうか。発達障害の中でも限局性学習障害(以下 SLD)は軽度知的障害や境界域と誤解されやすく、正しいアセスメントの元に適切な支援を実践することが難しい。知的障害、怠学のケースまでひとくくりにSLDという捉え方をしてしまう教員が教育現場の多くを占めてはいないだろうか。
こう聞くと教員の知識やスキル不足に問題があると捉えられるかもしれないが、そういうことではない。SLDの捉え方が医療分野と教育分野で異なるため、学校側がSLDを疑ったとしても、医療機関では異なる診断を示す場合がある。知的障害があると感じられる児童の保護者が特別支援教育に拒否的な態度を示す場合、学校も本当は違うと分かっていながら、SLDの疑いがあるという理由で比較的受け入れやすい通級の利用を勧め、それから固定学級への転学を促すケースもよく見られる。逆に教育にある程度関心の高い保護者の場合、実際には知的障害や怠学と思われる児童をSLDだとみなして、他の考えを受け入れないこともある。このような諸事情のために、それぞれの立場から都合のよい形でSLDという言葉を使っているケースが多く、ますますSLDを正しく捉えることが難しくなっている実態が見られる。
この研究の目的は、SLDを正しくアセスメントするための知識やスキルを整理した上で、SLDをもつ児童・生徒とその家庭が、個々の特性に合った支援や自助努力の方法を選択できる環境を提供することである。なお、アメリカ精神医学会が発行するDSM-5から、学習障害は正式には限局性学習症と表記することになっているが、日本では学習障害という呼び方が一般的であること、本文が文部科学省の定める学習障害の定義に沿った内容であることから、ここでは限局性学習障害(SLD)と表記している。












