
学校法人浅野学園 浅野中学・高等学校 小山 悠太
CO2 濃度計を用いた呼吸・光合成速度の定量化とバイオチャーによる環境改善の模索
Quantification of respiration and photosynthesis rates
第62回下中科学研究助成金取得者研究発表より
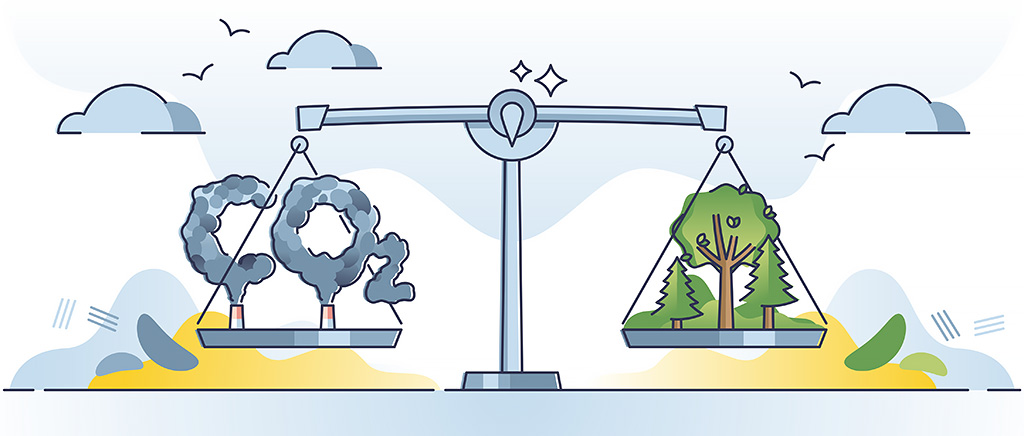
本校の豊かな自然を活かし、銅像山に生育する植物を用いた実験や森林生態系における物質収支の測定を行うことで、生徒の探求心の向上や環境問題に対する意識改革につなげたいと考えていた。
1.研究の背景
1-1 現状の理科教育(生物)に対する課題感と改善策
現在の中学校・高等学校における生物の単元において、植物の代謝(呼吸や光合成)や世界や日本における植生とバイオーム、生態系の多様性などを学習する時間は大きな割合を占める。また、環境汚染や地球温暖化の進行に伴い、国連では持続可能な開発目標としてSDGsに取り組む意向が採択されるなど、環境問題に対する関心も高くなってきている。日本では探求学習の重要性が示される一方で、授業時数は限られ、野外実験の実施は生物が少ない季節や雨が多い時期もあり、困難なこともある。また、生態系の多様性や保全に関する単元では教科書に掲載されている実験も少なく、映像や写真を用いて授業を行う場面が多い。よって、室内実験において生態系内の仕組みを定量化し、環境問題について議論できる授業を発案することが必要だと考えた。
生態系の物質収支(以下、「物質収支」)を学習するにあたり、生産者である植物の呼吸と光合成の関係を捉えることは重要である。一方で、呼吸や光合成に関する実験は、視覚的な判断に基づく定性的な実験(BTB溶液の色の変化など)が多い。また、中学校・高等学校において光合成におけるCO2濃度の変化を捉えた事例はあるものの、実験授業の確立や物質収支の比較には至っていない[1]。高校生物基礎の光合成曲線を学習する際も、CO2吸収速度は相対値で示されており、実際のCO2吸収量や放出量を生徒に伝えることが難しいのが現状である。
地球温暖化などの環境問題が深刻化する中、現象を伝えるだけでなく、実体験を通して学ぶことで環境問題への関心も向上すると考えている。また、学校における情報教育が求められる中で、理科実験にも積極的にICT教育を取り入れることは重要である。ICT教育を用いて環境教育を身近に学べる実験を開発し、生徒の研究活動に活用することは、理科教育の発展や生徒の探求心の向上につながる非常に意義深い取り組みであると考えている。
1-2 校内の山林を活かした取り組み
本校は神奈川県横浜市にあり、創立105年という歴史がある。58750m2の敷地の中には銅像山と呼ばれる山林を有しており、神奈川県の鳥獣保護区にも指定されている。銅像山は複数種の陽樹や陰樹によって構成され、様々な動物や植物が生育する貴重な森林生態系としても機能している。本校の豊かな自然を活かし、銅像山に生育する植物を用いた実験や森林生態系における物質収支の測定を行うことで、生徒の探求心の向上や環境問題に対する意識改革につなげたいと考えていた。












